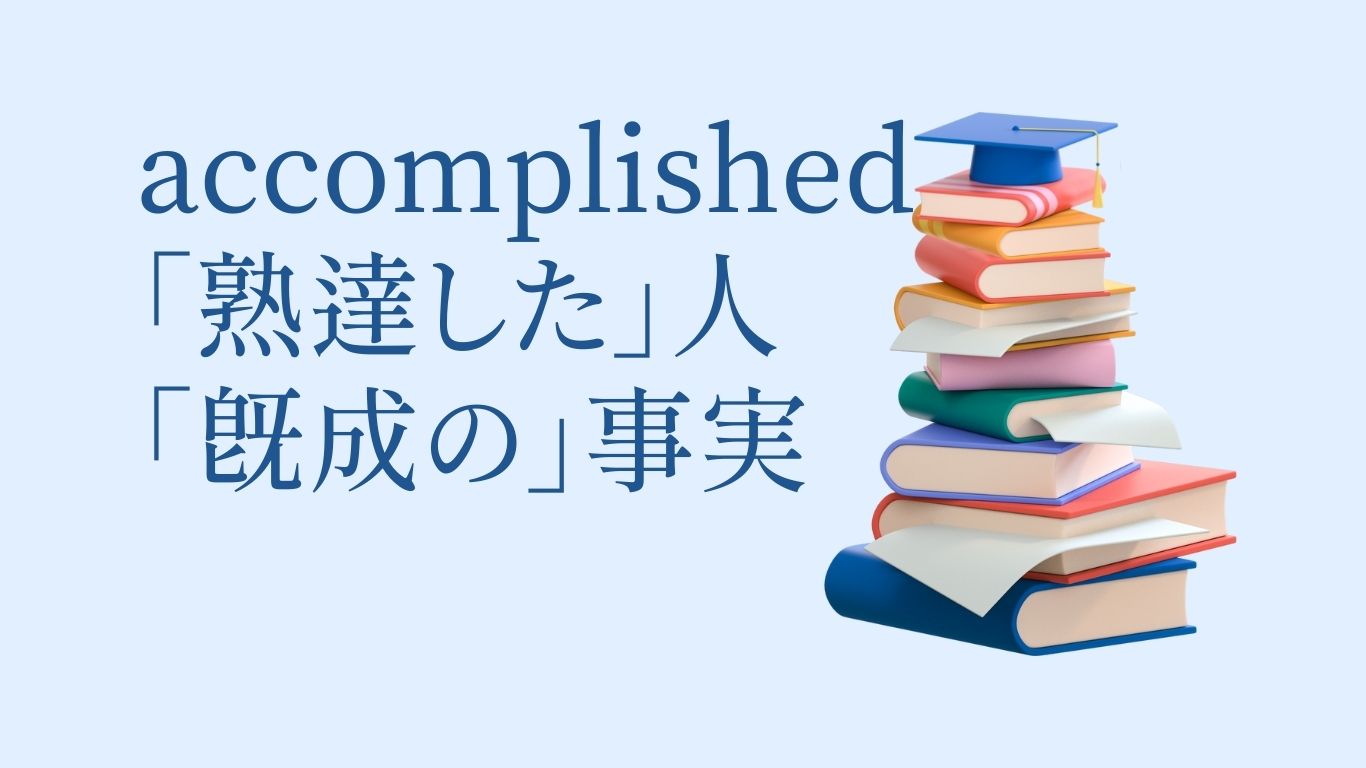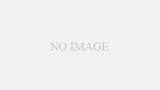accomplishedの意味
accomplishedはアカムプリッシュ(トュ) と読みます。accomplishedの語源は、com(complete)「徹底的な」です。語源から転じてaccomplishedは「熟達した」専門家や「既成の」事実という意味に使われています。accomplishedの覚え方として、「熟達した」専門家(an accomplished expert)、「既成の」事実(an accomplished fact)と覚えると覚えやすいでしょう。
本記事では、accomplishedの意味、読み方のコツ、語源、についてていねいにわかりやすく説明しています。例文を通して、accomplishedの意味や使い方をしっかりと学ぶことができます。本記事を読み終える頃には、accomplishedがしっかりと記憶に定着するでしょう。
accomplished 意味1 good at doing something that needs a lot of skill
accomplished 意味2 completedやdone
形容詞のaccomplishedと動詞accomplishの過去形・過去分詞形であるaccomplishedを混同しないように注意しましょう。
動詞としてのaccomplishは、「to succeed in doing something good」何か良いことをすることに成功する、つまり「何かを成し遂げる、達成する」という意味です。
「何かを成し遂げることができる」→「熟練している」から、形容詞の使い方(例 an accomplished pianist)と結びつけると覚えやすいですね。
動詞accomplishの例文も見てみましょう。
例文 I would like to accomplish my aim in life.
人生の目標を達成したいですね。
例文 He has accomplished a lot. (動詞の過去)
彼は多くを成し遂げた。
accomplishment という名詞もあります。
accomplishmentは、「something good that you have done that was difficult」難しい何かを成し遂げること、業績、完成、成就 という意味です。
達成感は a feeling of accomplishment と英語で言うことができます。
accomplishmentの例文を見てみましょう。
例文 His family is proud of all his academic accomplishments.
彼の家族は彼の学業での業績を誇りにしている。
例文 Cutting the budget was an impressive accomplishment.
予算を削減することで素晴らしい成果が出せた。
accomplishedの反対の意味を持つ単語として、incompetentがあります。
incompetentは、not having or showing the necessary skills to do something successfully. 「何かを首尾よくするのに必要な技術を持っていないかったり示したりしない」ことです。つまり、「無能な」人という意味です。
incompetentの例文を見てみましょう。
例文 Having made so many mistakes, he was forced to fire his incompetent secretary.
ミスが絶えないので、彼はやむなく無能な秘書をクビにした。
incompetentは、「法的に責任能力がない」という意味で法律用語としてよく使われます。
例文 The court finds that the defendant is incompetent and is likely to remain so for the foreseeable future.
裁判所は、被告人は責任能力がなく、予見可能な将来にわたって責任能力を持てない可能性が高いと判断する。
accomplished まとめ
accomplishedは、「熟〇した」専門家や「既〇の」事実という意味です。
「熟達した」専門家(an a….p..shed expert)
「既成の」事実(an a….p..shed fact)